

日時:2014年12月5日(金)
場所:京王プラザホテル
共催:ベックマン・コールター株式会社
第59回日本生殖医学会学術講演会・総会モーニングセミナー(ベックマン・コールター株式会社共催)にて、わが国のAMH臨床研究の先駆者である浅田義正先生が、AMHに関する最近の知見、AMH検査の有用性と課題、さらには新しい検査試薬「アクセスAMH」(研究用)への期待について解説されました。
座長:辰巳 賢一 先生(梅ヶ丘産婦人科 院長)
演者:浅田 義正 先生(医療法人 浅田レディースクリニック 理事長)
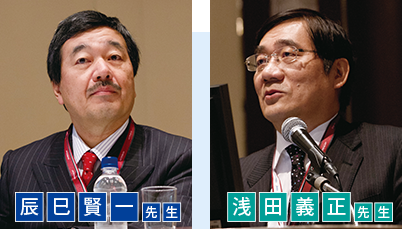
近年、卵子成熟過程で分泌されるアンチミューラリアンホルモン(anti-Müllerian hormone:AMH)は、卵巣予備能の評価指標として、不妊治療領域において注目を集めている。その一方で、AMHの特性やその測定意義については、十分なコンセンサスが得られている状態とはいえず、現在、研究が進められている。今回、第59回日本生殖医学会学術講演会・総会において、わが国でAMH臨床研究の先駆者としてご活躍されている浅田先生によるモーニングセミナー「AMH update-有用性と今後の期待-」(共催:ベックマン・コールター社)が開催された。AMHに関する最近の知見、AMH検査の有用性と課題や、さらに新しい検査試薬 「アクセスAMH」(研究用)への期待についてのご講演内容を紹介する。
卵巣予備能を卵子の質と量の面からみた場合、「卵子の質=年齢」、「卵子の量(数)=卵胞刺激ホルモン(follicle stimulating hormone:FSH)基礎値」と考えられてきた1)。しかし最近、卵子数については、アンチミューラリアンホルモン(anti-Müllerian hormone:AMH)が注目されてきている。その理由として、AMHはFSH基礎値と比べ、表1のような特徴をもつことが挙げられている2)。一方 、AMH値は卵巣予備能の参考になるもののその値の正確性は乏しいといったメタ解析を用いたシステマチック・レビュー3)があるほか、妊娠、卵子・胚の質の予想に使用できない、正常値が不明瞭であるなど、AMHの測定意義を疑問視する意見も散見される。
AMH値はその特徴を十分に理解することで、患者さん一人ひとりの状態にあった適切な不妊治療方針を検討するための有用な指標となり得る可能性があると考える。そこで、当院での不妊治療におけるAMH値測定の有用性の検討について紹介する。
AMHは19番染色体上の遺伝子にコードされ、TGF(transforming growth factor)βsuperfamilyに属する糖蛋白である。AMHは胎生期の男児の精巣に発現し、Müller管の退行を促し、男児の生殖器を形成する4)。一方、胎生期初期の女児においては、Müller管は左右の卵管および子宮へと発達し、AMHは妊娠32週頃から胎児の卵巣において発現が認められる。成人女性の卵巣においては、AMHは原始卵胞では検出されないが、これからリクルートされて発育する卵胞、特に前胞状卵胞と小胞状卵胞(おおよそ径4~6mm程度)の顆粒膜細胞からは最も多量に分泌され、さらに発育が進むと発現は減弱する。卵胞液中のAMH濃度は、通常血中の約3倍であるが5)、卵胞径の増大に伴ってその濃度は低下する。このような事実から、血中AMH値は前胞状卵胞と小胞状卵胞の数(プール)を反映しており、卵巣予備能の評価として有用であると考えられている6)。またこのような特性から、他のマーカーと違い、AMH値は月経周期に左右されないと報告されている7)。
AMH値の特徴として、全体としては年齢とともにAMH値は減少する傾向にあるものの年齢に相関せず、個人により値にばらつきが大きい点が挙げられる。国内外の複数の研究からも、年齢に対しては正規分布を示さず、同一年齢層における標準偏差も非常に大きいことが報告されている8,9)。また、このことから、AMH値は基準値を設定し、正常か異常かを診断する値ではないと考える。
また、年齢は妊娠率と相関するが、AMH値と妊娠しやすさは相関しないことも知られている。つまり、AMH値による卵巣予備能の評価は、妊孕性の評価ではなく、不妊治療が可能な期間を予測する指標と考える。
AMH値が検出限界レベルの限りなく0に近い女性でも妊娠および出産する可能性はあり、実際に、当院ではそうした妊娠例や出産例を経験している。低AMH値例に対しては、残存する卵子数を予測することでその機会をいかに有効に使うかを考え、いたずらに時間を費やすことなく早期に治療段階をステップアップし、1~2年で結果を出すよう目指した方が良いと考える。また、低AMH値例の患者には、妊孕性が低いと断じて落胆させるのではなく、「短期間しか治療できないので頑張ろう」と励ますよう言葉をかけることが大切であろう。
AMH値の有用性として、体外受精の際の採取卵子数とよく相関する点が挙げられる。当院で体外受精を行った1399名について検討したところ、AMH値と採取卵子数は正の相関を示した(AMHと採取卵子数図1)10)。当院では、AMH値も参考にして採取卵子数を予測し、年齢に応じた調節卵巣刺激法を選択している(図2)。また、高AMH値例に調節卵巣刺激を行う場合には、卵巣過剰刺激症候群(ovarian hyperstimulation syndrome:OHSS)を予防する刺激法を検討する一助となる。
従来、AMH値測定における問題点として、①変動係数が大きい、②測定値が不安定、③溶血等の影響を受けやすい、④補体の干渉が大きい、⑤研究用試薬である、といった点が指摘されてきた。特に補体の干渉については、酵素結合免疫測定法(ELISA)による測定試薬「AMH Gen Ⅱ」を用いた場合、ウェルに固層化された抗AMH IgG抗体に検体中の補体C1qと、補体カスケードによって急激に産生されたC3bが検体中のAMHよりも先に結合してしまうことで起きる現象である。新鮮な検体ほど干渉が強く、AMH値が低く検出されることが判明し、2013年7月より測定工程が一部変更された。
補体干渉のほか、溶血などの影響を受けることもあり、AMH値の測定誤差は約±15%と大きいのが「AMH Gen Ⅱ」の現状である。臨床においては、AMH値が上昇するケースもあり明確な説明が困難であるが、このような誤差を念頭に入れた診断が必要である。今後、測定精度が向上することでなんらかの結論が得られることを期待したい。
なお、過去に検査試薬が「EIA AMH/MIS」から第2世代の「AMH Gen Ⅱ」に切り替わった際、記載単位がpMからng/mLに変わっているため、データを比較する際に注意が必要である。
そのようななか、新たなAMH測定試薬として、2014年10月に自動測定装置用の「アクセスAMH」(研究用)※が発売され、測定精度が高まることが期待されている。
従来の「AMH Gen Ⅱ」は、補体の影響を抑制するための検体の前処理(希釈操作)を要し、プレートを用いた用手法のELISAであるため、操作が煩雑で測定時間も長かったのに対し、「アクセスAMH」は専用の全自動測定装置を用いることにより、検体の前処理が不要(装置内で自動希釈)で、検体の追加測定も随時可能であり、測定時間も40分と短時間で測定結果が得られる(表2)。また、「アクセスAMH」ではELISAではなく化学発光酵素免疫測定法(CLEIA)を使用して測定するため、低濃度域の感度にも優れ、より安定したAMH値が得られるものと期待される(図3)。今後は、「アクセスAMH」による日本人データの集積に注目していきたい。
※
アクセスAMHとは、ベックマン・コールター株式会社が販売する化学発光酵素免疫測定法による自動測定装置用試薬(研究用)を示します。
詳しくはベックマン・コールター株式会社までお問い合わせください。
AMH検査は不妊治療の現場に限らず、一般産婦人科においても有用である可能性があると考えられる。たとえば、月経異常が認められる場合に血中AMH値測定を行うことで、早発卵巣不全の可能性の有無を早期に疑い精査に進むことができる。また、女性のよりよいライフプラン選択という観点からも、30歳を迎えたら未婚・既婚にかかわらず、一度は計測する価値のある検査であると考えている。現状では検査は研究用試薬によるものであるが、今後、AMH検査の研究が進み、その有用性が明らかになることを期待している。